「シェイプ・オブ・ウォーター」(2017)
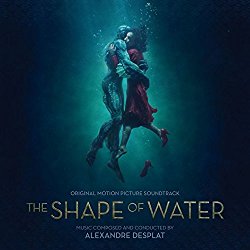
監督
ギレルモ・デル・トロ
キャスト
サリー・ホーキンス(イライザ・エスポジート)、マイケル・シャノン(ストリックランド)、リチャード・ジェンキンス(ジャイルズ)、ダグ・ジョーンズ(半魚人)、マイケル・スタールバーグ(ロバート・ホフステトラー)、オクタヴィア・スペンサー(ゼルダ)
映画は赤の歴史だった。モノクロ全盛期にテクニカラーで衝撃を与えた「オズの魔法使い」(1939)の有名な靴は赤だったし、レッド・パージはハリウッドを崩壊させたわけだし、ゴダールが必要にアヌーシュカに着せたのも赤の服だった。この映画のセットにだって、「赤い靴」(1948)の窓があるじゃないか。映画内設定の1964年には「赤い砂漠」(1964)が上映しているし。赤は常に映画を支配してきた。映画から赤が狩られることはなかったのだ。
この映画のカラー(緑と赤)の秘密ならば、ネットの海にガラクタのように散らばっている。色の補色関係でそれを紐解くものもいれば、製作者のインタビュー記事から考察するもの、映画の中のセリフから読み解くものもいる。だから、なぜこの映画のキートーンが緑で、赤がアクセントとして使われてたのかという意味を知りたい方は是非、他のページを見ていただきたい。実際にそっちの方が真実に近いかもしれないし、トリビアとしてあなたのインテリジェンスのストックにもなるだろうし、それで映画が面白くなるのなら絶対にそっちの方か良い。だからここでは、もっと個人的な映画史や映像史に沿って打ち込みをしていきたい。
「緑」と「コントラスト」
とはいえ、この秘密に関してある程度の説明は必要でもある。その秘密のキーとなっているのが「緑」という色と「コントラスト」だ。そもそもこの映画はモノクロ映画として企画されたのだったが、カラー版のラッシュか何かを観た監督が、カラーへと変更を決めたらしい。監督のギレルモ・デル・トロや、衣装のルイス・セクエイラ、ラボを設計したオスターベリーなどの制作陣は、ロマンチックな場所(イライザ(サリー・ホーキンス)と半魚人(ダグ・ジョーンズ)が恋に落ちる場所)をロマンチックにしないために「緑」を使用していると語っている。この映画では「緑」はロマンチックじゃない結末(ジェロゼラチン、車(鴨の色)、イライザの服)と関係性を強く結んでいる(ちなみにRGBを同じ信号の強さで発信した場合、緑が一番明るく感じ、青が一番暗く感じるようになっている。つまり、明るい世界はアン・ロマンチックだと彼らは言いたいのだ)。
そしてもう一つの「コントラスト」。上にも述べたが、ロマンチック(意味)とアン・ロマンチック(表象)のコントラスト。イライザの家(シアン系)と他の家(アンバー系)の色彩とライティングのコントラスト。身体や心身に不具を抱えた人物と、彼らの演じる傲慢さというコントラスト(決して不具者を悲哀の対象として二元論化しているのではなく、それが物語に同情の誘い水として使用されているかいないかという問題。欠落による同情。ユング的な共時性という視点)。1964年のファッション(ツィギー、マリアンヌ・フェイスフル)と1964年設定という映画内のファッションのコントラスト。この映画にはとにかくあらゆるコントラストが散りばめられ、巧妙にロマンチシズムに陥らないようにできている。そして最後に、この映画の最も重要なコントラストが、イライザの衣装の時間的コントラスト(緑→赤)なのだ。
赤はどうしてもスクリーンに映える不思議な色だ。この映画の時代設定である1964年に上映された「シェルブールの雨傘」(1964)は、映画の初めから最後まで至る所に赤い衣装が配置されている。ジャック・ドゥミは、この全編歌劇という狂信的な映画に惜しみなく赤を配置した。一方で「ロシュフォールの恋人たち」(1967)では、赤い衣装はお祭りのシーンにしか姿を見せない。この映画はチラリズムの映画(ダンサーのパンツがチラチラ見えたり、男たちがフランソワ・ドルレアックに悪気もなく「下着が出てますよ」と言ってのけるその自然な仕草からも、この映画がチラリズムの映画だということがわかる)なのだが、その世界観をこの赤い衣装の使い方(チラリズム)によって見事に作り出した。ジャック・ドゥミは、間違いなく赤という色に敏感だった。つまり、それがいかにして物語に影響を与えていくかということへの感度が素晴らしかったのだ。
何も映画だけではない、中平卓馬やエグルストンの写真にだって赤は配置されている(彼らのカラー写真における転覆したモダニズムに関してはいずれ機会があれば語りたい)。
そして、この映画にも「赤」は登場する。イライザのカチューシャが、映画の途中で緑から赤に変わる。そして、服装までもが赤に変わっていくのだ。「アン・ロマンチックからロマンチックへの移行!」「恋の物語が進展するにつれ、突如として色彩を持ち始めたこの映画!」と言えばすごくわかりやすい映画評だが、もうそんなことはどうだっていいのだ。このあまりにも単純でわかりやすい、巧妙でもなんでもない赤の使い方に、僕はとことん痺れてしまったのだ。なんだろうかこのバカバカしさは。アメリカよ、いいじゃないか!と言いたいのだ。人間と半魚人のミュージカル?(この映画には、一度だけモノクロになるシーケンスがあり、それはイライザと半魚人によるミュージカルなのだ!)いいじゃないか!最高だ。そうなったらもうだめだ。恥じらいもなく告白させてもらえば、半魚人がイライザを抱きかかえて海へと飛び込んでいく姿を見て僕は涙を流したのだ。数年前の僕なら(ハリウッドアレルギー)考えられない。僕が変わったのかアメリカが変わったのか。